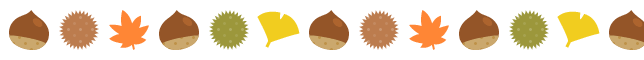 | |||||
のネブカデネツァル王の軍隊に捕えられ、バビロニヤに連れて行 かれた。1000kmにも及ぶ荒野、砂漠の中の道のりを、3000人から 4000人の同胞と一緒に連れられて行った。彼の心境について記さ れていないけれども、詩編の中に捕囚の民の歌がある「バビロン の流れのほとりに座り、シオンを思って、わたしたちは泣い た。」(詩編137:1)と。50年にも亘った捕囚の地での生活で、彼 は詩編の詩人のような思いを抱きながら過ごしたであろう。そし て、祭司であった彼は、「いつの日か神が回復してくださる、罪 を赦し、エルサレムに連れ帰ってくださる。」その信仰を、捕囚 の地で悲嘆にくれる同胞たちに語り続けたであろう。 主の手がバビロンの流れのほとりでエゼキエルに臨んだのかど うかは分からないが、彼は連れ出され見せられた、枯れた多くの 骨を。そして主に言われるままに語ると骨は合わさり肉体が生じ たが、まだ霊はみられなかった。更に「霊よ、四方から吹き来た れ」と告げると、彼らは生き返って、非常に大きな集団となった という。息を吹き入れて生きるというのは、創世記の人間の創造 の時と同じである。そこでは人は神の息が吹き込まれて生きるも のとなると記されている。 しかし、今日の日課は、人がどうして生きるものとなったかを 語ろうとしているのではない。イスラエルの民は生きてきたので あるが、彼らの様はまるで枯れた骨だという。しかも甚だしく枯 れていたと。つまり捕囚にあったイスラエル、神の民の群れは、 甚だしく枯れた骨だと言っているのである。なぜそうなのか、捕 囚の民だからか?荒廃した地に住んでいるからか?だとしたら捕 囚を解かれたら生きるのか?豊かさを取り戻せば生きるのか? エゼキエルに語られた言葉の中心は、「わたしが」即ち「主 が」である。イスラエルの民に、バビロンの流れのほとりで涙す るものに、「私が共にいる」涙をぬぐえる力を与えるといってく ださっているのである。 聖霊降臨日、教会が誕生した。霊なる神が降るのである。それ は主が共にいてくださるしるしをくださったということにほかな | |||||
| らない。エゼキエルに臨んでくださっ たように、私たちが涙する時に聖霊が 「泣かないでいなさい」と語ってくだ さるのである。涙しない日々を送るこ とが出来るように祈っています。 |  | ||||
| |||||
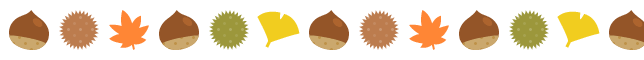 | |||||
